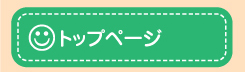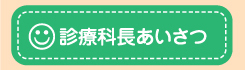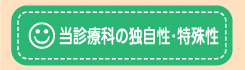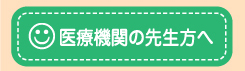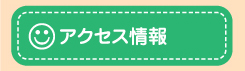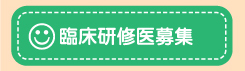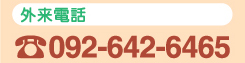全身麻酔下で治療を行う場合の注意点
全身麻酔下で治療を行う場合の注意点には、大きく分けて2つあります。ひとつは歯科治療にかんするもの、もうひとつは全身麻酔という麻酔方法にかんするものです。歯科治療、とくにむし歯治療にかんする注意点
- 神経まで進んだ深いむし歯の治療について
乳歯も永久歯も、神経の奥まで進んだ深いむし歯の治療は、通常は1回では終わりません。根の消毒や殺菌をていねいに繰り返してから人工材料を中に詰めます。最後に冠を被せてやっと1本のむし歯治療が終わります。ところがこれを毎回、通院のたびに全身麻酔下で行うことは出来ません。こどもの体の負担が重すぎるからです。
全身麻酔下で深いむし歯の治療をするときは、これらの過程を一度で済ませます。ステップごとに数日間様子をみて十分に殺菌できているか、症状が改善しているかなどの確認はできません。一度限りですべてを判断するのでリスクを伴います。判断が甘ければ、治療のあとすぐに痛みや腫れが出て、全身麻酔下で治療をやり直すことになるかもしれません。このような事態をできるだけ避けるために、むし歯が深く進んで神経が侵された歯は、より厳しく判断して抜歯となることがあります。 - むし歯治療とそのあと、むし歯が治っていく経過について
大切なことは、治療したその日にむし歯が治ってしまうわけではない点です。
むし歯治療とは?:
むし歯治療の第一段階は、むし歯菌が感染した病巣を除去する(悪いところを取り除く)ことです。1本の歯の中でむし歯菌に感染した部分を機械で削り取り、そこを人工材料でもとの歯のような形に再建します。もっと重症でむし歯菌が歯の全体に感染してしまった場合は、歯をまるごと除去すること(=抜歯)が必要です。このように“むし歯治療”には、“歯とそのまわりの歯肉・骨などの組織に一時的に傷をつける行為”という一面があります。持って生まれたからだの一部である歯が、治療上、必要に迫られたものであったとしても、また一時的なものであったとしても傷ついてしまうことに変わりありません。
むし歯が治っていく経過とは?:
むし歯治療の第二段階は、“歯とそのまわりの歯肉・骨などの傷ついた組織”の回復させることです。“むし歯が治っていく経過”とは、“歯とそのまわりの歯肉・骨などの傷ついた組織が回復していく経過”と言い換えることができます。その経過には、数週間から時には数カ月以上もかかることがあります。また回復の途中で、化膿して応急処置が必要なこともあります。“歯とそのまわりの歯肉・骨などの傷ついた組織”が順調に回復しているかどうか、定期的に診察や検査を受けていただく必要があります。また傷の回復をうながすために日常生活の節制や口腔ケアを行い、自然治癒力を高めるよう心がけてください。
大切なことは?:
全身麻酔下でのむし歯治療は、 10本でも20本でもたった1日で終わらせることができます。麻酔から覚めたあと口の中をみると、歯にプラスチックや金属の冠がきれいにかぶせてあり、一見すると歯が傷ついているようには思えません。もうむし歯がすっかり治ってしまったかのように思えます。しかしそれは錯覚です。傷ついた歯が治るまでには長い時間がかかること、油断すると途中で化膿したり症状がぶり返すかもしれないことを忘れないでください。このような注意点は、からだの部位は異なりますが、たとえば虫垂炎で盲腸の手術を受けた場合の注意点と同じです。
- 治療日までの体調管理について
全身麻酔がかけられなくなる体調不良のなかで、こどもに最も多いのが風邪やインフルエンザなどの感染症です。発熱・くしゃみ・咳・鼻水などの症状がある場合は全身麻酔による合併症のリスクが高くなります。全身麻酔がかけられず、治療も延期になります。術前検査のあと、治療日前の2週間の過ごし方がとくに大切です。この期間は絶対に油断せず、体調管理・節制・口腔ケアに気を付けてください。これは治療後に“傷ついた組織”の回復をうながすことにもつながります。こども本人だけでなく、ご家族全員の協力が大切であることをご理解ください。
九州大学病院小児歯科・スペシャルニーズ歯科では、現在、全身麻酔下での治療を毎週3例(月・水・木に1例ずつ)行っています。しかし全身麻酔下で行う必要があるこどもは多数います。現在のところ、およそ2カ月先まで予約が詰まっている状態です。体調をくずして直前にキャンセルになると予約をとり直さなければなりません。しかし次の予約日は現在のところ、およそ2カ月先になります。むし歯はその間に深く進行していきます。治療日が決まった方は、風邪などの体調不良でキャンセルにならないよう、くれぐれも体調管理にご協力ください。
ちなみに2009年4月から2011年3月までの2年間で予定されていた277例の全身麻酔症例のうち、体調不良で予定が中止となった症例は70例(約25%4人に1人)でした。 - 全身麻酔がきっかけで起こる症状(合併症)について
全身麻酔は体調管理と安全確認をしっかり行えば、合併症の頻度は極めて低いことが知られています。それでも合併症はゼロではありません。全身麻酔がきっかけで起こる症状(合併症)には様々なものがあります。ここでは代表例をいくつか挙げて簡単に説明しておきます。くわしい説明は、小児歯科の担当医と歯科麻酔医が行います。全身麻酔がきっかけで起こる症状について、わからないことや不安なことがありましたら、小児歯科担当医と歯科麻酔医に遠慮なくお尋ねください。- 喉頭けいれん・気管支けいれん・肺炎
麻酔の刺激で喉や気管支がけいれんし呼吸障がいを起こすことがあります。またかぜ症状がひどくなり肺炎にかかることがあります。これらはすべて、元気で健康なこどもに全身麻酔をかけた場合にも起こりえます。しかしかぜ症状があるこどもに無理に全身麻酔を強行したときさらに起こりやすくなります。生命にかかわる緊急手術の場合は、やむをえず全身麻酔を強行せざるを得ないことがあります。しかし小児歯科・スペシャルニーズ歯科で行う治療の場合、このような緊急性があることはごくまれです。体調が十分に回復するまで全身麻酔を避けた方が安全です。薬をのんで症状をおさえているだけという状況は、危険です。かぜ症状が本当に改善しているかどうかを確認するため、かかりつけの小児科医師の診察をうけていただくこともあります。冬場はインフルエンザなど、かぜ症状を繰り返すこどもが多いので、体調管理が特に重要です。参考までに乳幼児のかぜの程度を評価する、かぜスコアを示します。評価項目のうち“発熱がある・咳や痰がひどい”という場合は、かぜの急性期とみなしそれだけで全身麻酔は中止となります。しかしその症状が鼻汁だけのような場合は判断に苦しみます。
乳幼児期はしょっちゅう、かぜを繰り返します。そのため中止を2度3度繰り返すこどももいます。全身麻酔をかけることができるか否かの判断は、予定通りかつ安全に全身麻酔をかけて処置をしたい小児歯科担当医・歯科麻酔科医ともに常に頭を悩ます問題であることをご理解ください。
九州大学病院では単にかぜスコアに基づいて画一的に判断しているわけではありません。これはあくまで判断材料のひとつです。乳幼児のかぜスコア 診査項目(各1点) 1.鼻閉、鼻汁、くしゃみ 6.食欲不振 2.咽頭発赤、扁桃腫大 7.胸部エックス線写真異常 3.咳、喀痰、嗄声 8.白血球増多
(乳児12000、幼児10000/mm3以上)4.呼吸音異常 9.かぜの既往
(入院前2週間以内)5.発熱
(乳児38度以上、幼37.5度以上)10.年齢因子(生後6カ月未満) かぜスコア 0〜2点:健常群 3〜4点:境界群 5点以上:危険群 - 喘息発作
麻酔の刺激で発作が誘発されることがあります。喘息の治療を受けているこどもはもちろん、過去に治療を受けたことのあるこどもで数年間、発作が出ていないこどもであっても、注意が必要です。喘息の治療中(薬を使っているこども)の場合、最後の発作が起きてから1カ月以上は全身麻酔を避けた方がよいこともあります。保護者の方には、喘息の症状と治療の経過についてくわしくお聞きします。症状と経過によっては喘息を診察してもらっているかかりつけの小児科医師とも相談の上、治療計画を立てます。 - 悪性高熱症
全身麻酔中に全身の筋肉に異常をきたし、体温が急激に上昇して危険な状態になる病気です。まれに全身麻酔が終わったあとに起こることもあります。全身疾患を抱えるこどもや、血縁者に麻酔で異常な反応を起こした方がいる場合などでは悪性高熱症の危険が高まります。悪性高熱症の危険が高いことが予測できるこどもの場合は、全身麻酔を避けるか、全身麻酔に用いる薬剤を工夫する必要もあります。悪性高熱症の危険がきわめて低いと予測されるこどもに起こることもごく稀にあります。 - その他の症状
吐き気、おう吐、喉の痛み、かすれ声、誤嚥、誤嚥が原因で起きる肺炎など、麻酔から覚めたあとに出ることがあります。また、麻酔をかける操作の時に、ぐらぐらした歯が抜け落ちることがあります。歯科領域では、この“ぐらぐらした歯”は全身麻酔とは関係なく、常に注意を払っています。
- 喉頭けいれん・気管支けいれん・肺炎
- 予防接種を受ける時期について
予防接種を受けたあとしばらくのあいだ、全身麻酔をかけることを避けた方がいいでしょう。では予防接種を受けたあと、どのくらいの期間が過ぎれば全身麻酔を安全に受けることができるでしょうか。これについて、正確な根拠に基づいた絶対的な基準はありません。しかし一般的に予防接種を受けてから1カ月以内は、全身麻酔を避けた方が安全とする施設が多いようです。予防接種を受けたあと、しばらくのあいだからだの中で防御反応(免疫応答)が起こります。この防御反応(免疫応答)をわざと誘導するのが予防接種の大事な目的です。ところがこの防御反応(免疫応答)の結果、しばらくのあいだ風邪症状とまぎらわしい症状が出ることがよくあります。そのため本当の風邪症状か、予防接種で誘導された防御反応(免疫応答)か、われわれも判断に迷います。また複雑なことに、このような防御反応が表れる期間や症状の程度は予防接種の種類により数日から数週間のちがいがあります。そこで九州大学病院では予防接種の種類に関係なく、接種後は最低1カ月あけて全身麻酔を行うようにしています。全身麻酔による歯科治療・手術の予定日を決めるときは、予防接種を受けるスケジュールも考慮してください。参考までに、予防接種を受けたあと、どのくらいの期間をおいたら全身麻酔を安全に受けられるかについて、資料を示します(香川哲郎:予防接種、感染症と小児の麻酔.Anesthesia 21 Century 10:1801-1804, 2008より改変引用)。
では全身麻酔を受けたあとは、いつ予防接種を受けたらいいでしょうか。これについても、正確な根拠に基づいた絶対的な基準はありません。しかし全身麻酔や歯科治療・歯科手術のあと、一時的にからだの防御反応が低下することは確かです。十分に回復してから予防接種を受けた方が予防接種の効果が出やすいといえます。目安として全身麻酔のあと1カ月程度は予防接種を控えたほうがいいでしょう。ただしこの場合も予防接種の種類によって適切な接種時期がちがいます。全身麻酔を受けたあと、いつ予防接種を受けたらいいかわからない時は、小児歯科担当医のほか、かかりつけの小児科医にも相談してください。予防接種を受けたあと、どのくらいの期間をおいて全身麻酔をうけたら安全か? ワクチンの種類 ワクチンの具体例 一般的基準 最短期間
(副反応がみられる期間のみ空ける)生ワクチン ポリオ、麻疹、風疹、麻疹風疹混合、BCG、流行性耳下腺炎、水痘 4週間 3週間(21日) 不活化ワクチン 三種混合ワクチン(ジフテリア、百日咳、破傷風)、インフルエンザ、日本脳炎、B型肝炎、肺炎球菌、インフルエンザ菌b型(Hib)ワクチン 2週間 2日